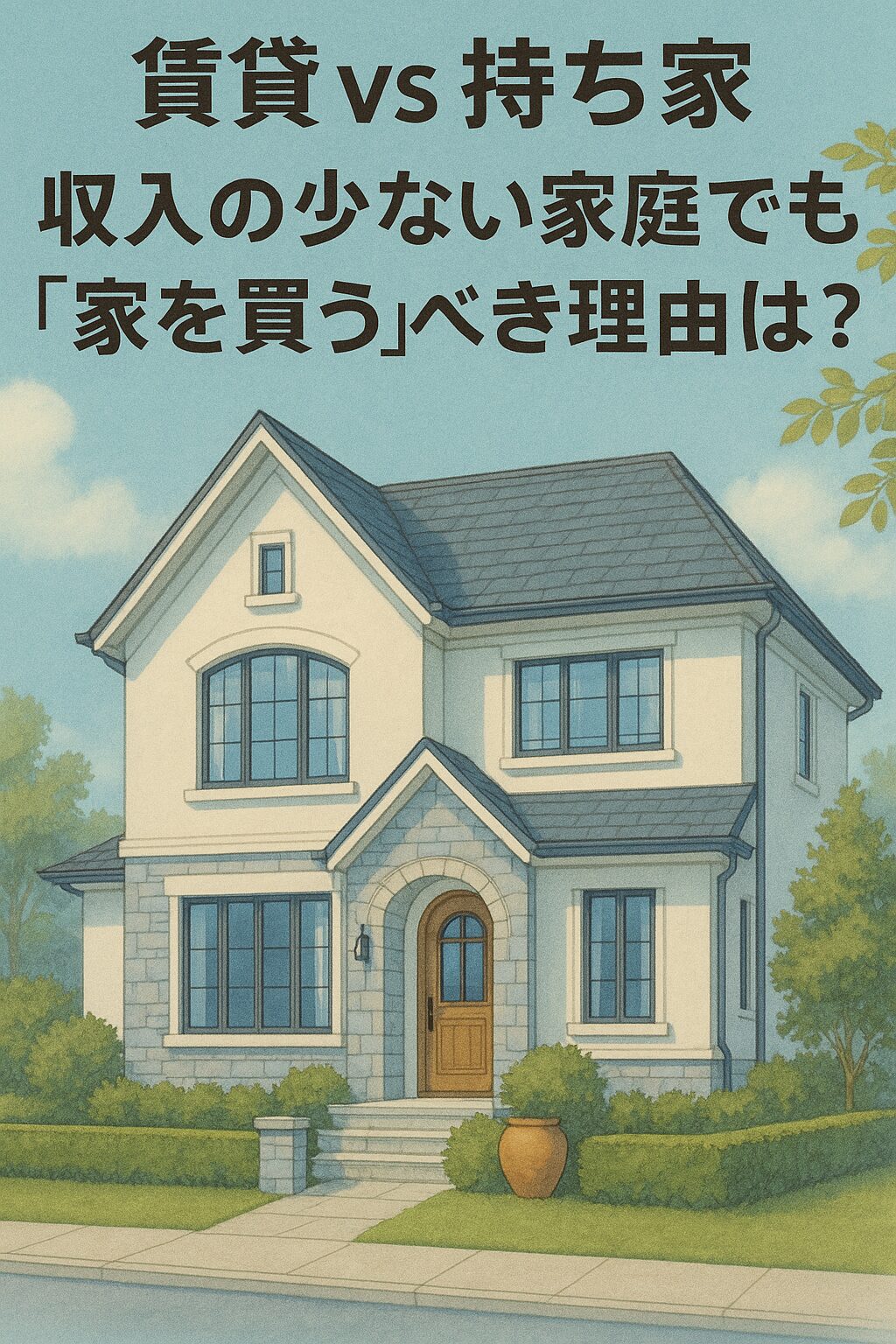こんにちは、ばっきんパパです。
中古住宅を購入するにあたり、私は自分の判断に落とし穴がないかを確かめるために、専門書を繰り返し読み込みました。特に参考にしたのが、**高橋正典さんの『プロだけが知っている!中古住宅の買い方と売り方』(朝日新聞出版)**です。
この本には、耐用年数を超えた建物が「資産として評価されにくい」現実や、出口戦略(売却の考え方)まで、不動産売買の現場で積み重ねられた知見が書かれています。私は特に4ページにわたる具体例を何度も確認し、自分の購入判断に照らし合わせていました。
ただし本は“あらゆる立場の人”に向けて書かれているので、例えば「リフォームは資産価値を高める」といった一般論も登場します。
ですが私にとってリフォームは、資産価値のためではなく、現実に暮らしをより住みやすくするためのものです。
体験談を参考にしていただいたあと、ぜひこの本も読んでみてください。専門的でありながら読みやすく、中古戸建てを買うための役立つ内容が体系的に詰まっています。
暮らしは「想定外の連続」です
私の実家は、建築士さんにオーダーメイドで設計された家でした。
それでも、兄弟がいるのに子ども部屋が一つしかなかったことで、思春期は少しつらい思い出もあります。
家族構成は、思いがけず変わることもあります。他にも、住んでいく中でこんな変化はよくあります:
- 転職や転勤でライフスタイルが大きく変わる
- 両親の介護や、将来の同居を検討し始める
- 子どもの成長と共に、生活空間の使い方が変わる
- ご近所付き合いや学区の問題で、環境への満足度が変わる
- 離婚や別居など、人生の想定外の出来事が起きる
家は必ずしも「一生に一度の買い物」とは限らず、変化のなかで見直し続けていくものなのかも知れません。
私も買うとき怖かった:耐用年数と現実的な視点で
中古住宅という選択肢には、不安もあると思います。
- 築年数が経っているけど本当に大丈夫か
- 設備が古かったり、断熱性に難があるのでは?
- 修繕費やランニングコストが読めない
- 家の設計図すら残っていないことも多い
でも最近は、**「インスペクション(建物状況調査)」**という仕組みも整ってきており、「見えないリスク」は少しずつ可視化されつつあります。
さらに、建物の価値は「耐用年数」で評価されることが多く、ほとんどの中古戸建ては土地価格で売られているのが現実です。乱暴に言えば建物は“おまけ”のようなもの。若いうちはリセールバリューの観点からも「耐用年数を意識しつつ、使える間は使えばいい」というくらいの考え方でも良いのかもしれません。
知識が選択肢を広げてくれる
家選びに「正解」はありません。
けれど、「正しい知識」を持っていれば、選択肢を広げられます。
私の記事のような一次情報や経験談を読む→書籍やプロの情報で補強するという流れがあると、安心して決断ができます。
私も読み比べをし、各物件を比較検討した上で、収入の少ない経済的弱者でも、中古ならマイホームを持つことが正解の一つだと自信を持つことが出来ました。
私が、書き残しておきたい訳
やっぱり、“家を買う”という決断は勇気が要ります。
だから私は、誠実さを大切に、自分の体験を正直に綴っていこうと思いました。
私は終の棲家として暮らしていますが、中古戸建ては、もっと自由で、もっと楽しい。
そして専門書の知識も合わせることで、より安心して決断できると思います。
振り返れば、購入当時に「等身大の購入体験」が書かれたブログをもっと読みたかった。だからこそ今、私自身が発信する意味もあるかと感じています。
「家を買う」ことが、誰かにとっての「不安からの解放」になりますように。
※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています
続きの中古戸建て記事はこちら
👉 木造住宅の「法定耐用年数」は寿命じゃない?築30年の家に安心して住める理由