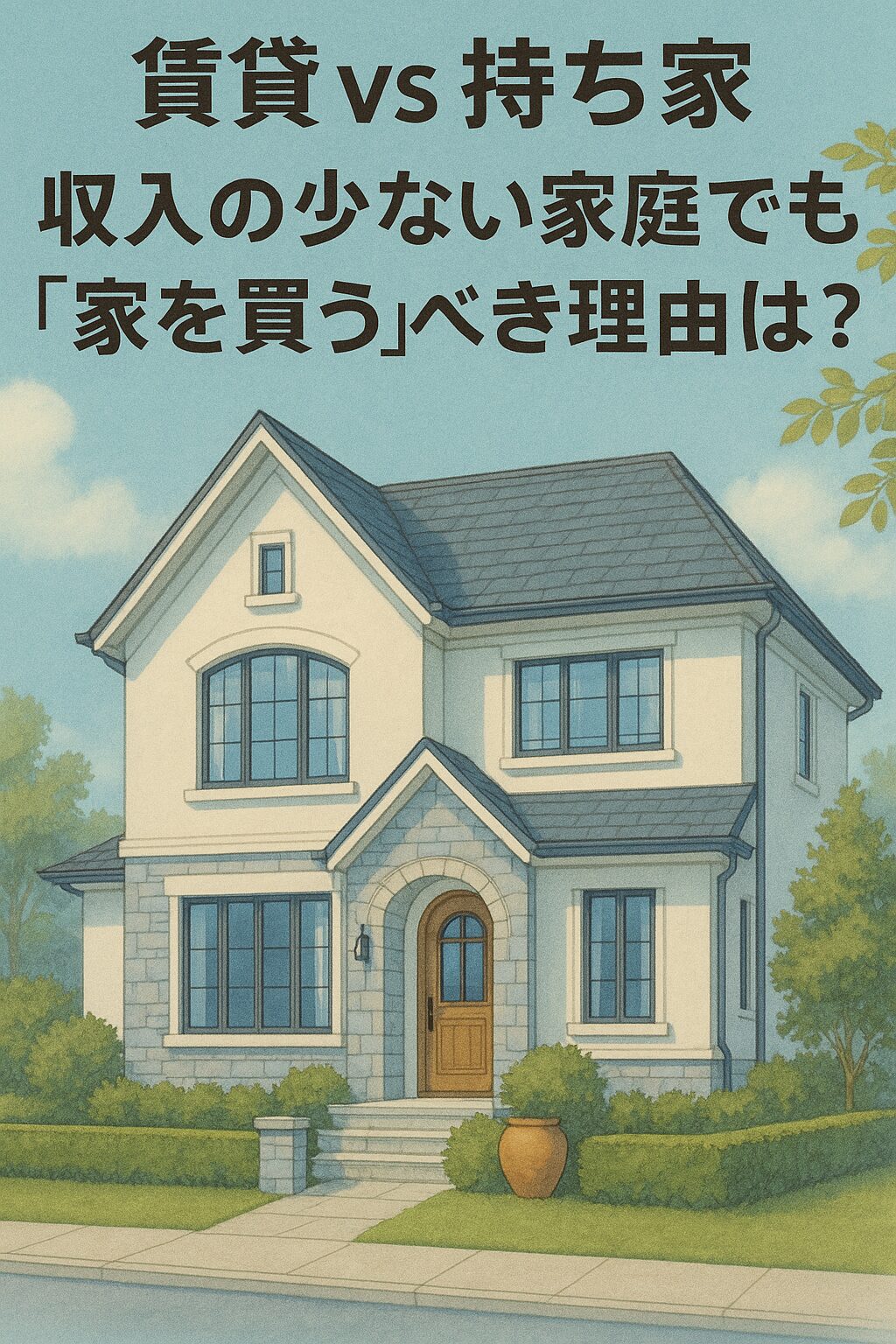はじめに:経済的弱者でもマイホームを持つべき理由
こんにちは、ばっきんパパです。
私は収入が多いとは言えない福祉職で、2児の父です。
正直に言うと、「無理して家を買うなんてリスクは高すぎやしないか」「新築、ましてや100点の物件なんて、無謀じゃないか」そう思いながら家探しをしていました。
それでも結果的に、私は築30年の中古戸建てを即決しました。
素人が頑張った取り引き内容としては70点で、色々失敗もしています。
でも、暮らしの満足度としては90点以上だと実感しており、このブログを残そうと思いました。
完璧な家ではありません。
でも、広い間取り・駅近・陽当たり・ご近所関係・住み心地まで含めて振り返ると、「この判断は間違っていなかった」と、今ははっきり言えます。
家の中心には太い柱があり、前面道路は広いが人通りは多くなく、車の出入りもしやすい。
見えにくい部分の住み心地も、決め手になりました。
この記事では、経済的に強くない立場から、なぜ「100点を目指さず70点で決める家選び」が現実的だったのか、私の実体験をもとに書いていきます。
賃貸vs持ち家論争──“賃貸派”が優勢な理由とは?
最近の“お金の勉強界隈”では「賃貸が合理的」という意見が主流です。
実は私も、持ち家には慎重派でした。
YouTubeで多くのマネー系動画や書籍では「賃貸がリスクを抑えやすい」と結論づけられています。
確かに、金利上昇やリストラでローン返済が滞る、転勤やご近所トラブルで住めなくなる、など、家を買ってしまうことの様々なリスクは沢山あります。
しかし、賃貸を続ける限り「家賃」という支出は消えません。
私のように収入が高くない働き方でも、最終的に“自分のもの”になる家を持ち、生活コストを固定化できれば、将来の安心感は段違いです。
答えは築古の中古戸建ての購入にありました。
▶リベ大・お金の大学を参考に判断したことについての記事はこちら

▶不動産Gメン滝島さんの動画を参考に判断したことについての記事はこちら

2,000万円でマイホーム購入を即決した5つの条件
私が中古木造戸建(築30年)を購入した決め手は、次の5点すべてがクリアだったから。
これが「法人投資家が見向きもしない」“掘り出し物”ゆえに、安く買えた秘訣です。
| 条件 | 理由 |
|---|---|
| ① 駅近で東京への通勤圏内 | 通勤・買い物に便利。再販売時も有利。 |
| ② 閑静な住宅街で前面道路が6mの広い公道 | 日当たり良好&駐車もラク。子育てにも安心。 |
| ③ 5LDK と余裕のある間取り | 育児スペース、書斎、将来の介護にも対応。 |
| ④ リビングが広く南向きで陽当たり良好 | 一日中明るく風通しも良い。 |
| ⑤ 家の中心に太い土台柱 | 構造躯体がしっかりしており、100年住める頑丈さ。 |
何よりこれらが揃って2000万円以下。自己資金とローンで無理なく支払える範囲でした。
▶購入時に重視したのは陽当たり。断熱については、ある程度割り切って選びました。


▶実際の住み心地についての感想についてのまとめは、こちら。

「耐用年数22年」は家の寿命じゃない
税法上の木造住宅の耐用年数は22年ですが、これはあくまで減価償却のための数値。建築学の研究では――
「適切なメンテナンスを続ければ、木造住宅は60〜100年超の寿命がある」
(東大・前真之准教授、早大・大野名誉教授ほか)
実際、日本の住宅は「建て替え文化」で30〜40年で更新されがちですが、本来は100年住めるポテンシャルを秘めています。
売り出されている中古住宅は、築20~30年も経つと物件価格が下がりきっています。
上物をほぼタダ同然で買えるので、総合70点の取引だったとしても、十分お釣りがくるのです。
▶そもそも不動産を買うことに対する不安についてはこちら

築年数で価値が消えても、住み心地は消えなかった
住んでみて一番驚いたのは、この家が「当時はかなりお金をかけて建てられている」と感じる場面が何度もあったことです。
太い柱、造作の丁寧さ、間取りの余裕。細部を見るほど、手抜きのない家だと分かってきました。
それでも、この家の評価は築年数だけで大きく下がっていました。
中古住宅の世界では、「どんな家か」よりも「何年経ったか」が先に見られる。
住んでみて初めて、私はその現実を実感しました。
結果的に私は、上物の価値がほぼゼロ評価になった家を、住み心地ごと手に入れた形になりました。
これは狙ってできたというより、あとから気づいた“構造的な得”でした。
良い買い物だった理由|価値のズレを拾えたこと
今振り返ると、私の買い物がうまくいった最大の理由は、「建てたときの価値」と「買ったときの価格」が大きくズレていた家を選べたことでした。
築年数で評価は下がっても、住み心地・構造・立地は、そのまま残ります。
この当たり前の事実に、住んでから気づきました。
結果として私は、建築コストの高い家を、土地値+αで手に入れたような買い物になっています。
上手な取引かだけを見れば70点だったかもしれませんが、買い物としては、正直120点だったと思っています。
手元資金は投資に回す―我が家の場合
- 家賃支出を抑える → 同じ支払額で「自分の資産」を手に入れる
- 月々の余裕資金でインデックス投資 → NISA・iDeCoで税優遇を活かす
- 将来、子どもの学費や老後資金を確保
…という家計シナリオです。日本人の貯蓄の中央値200万円というデータを見ると、“家を持つ→投資する”流れがいかに効率的かがわかります。
▶このブログでは家計管理もテーマにしています。投資についての記事はこちら


まとめ
- 賃貸が無難なのはリスク回避の観点。ただし、家賃という「消えもの支出」を固定化し続けない
- 駅近・陽当たり・構造の良さ・間取り…を「低価格で」手に入れられる物件に、法人が入りにくい
- 「耐用年数22年」は経理数字であって、実際は60〜100年住み続けられる
- 生活の安心基盤としての家と、将来のための投資は両立できる
このノウハウは、特に、収入が大きくない方ほど威力を発揮します。私は、ブログを書く前に、私と同じような収入の仕事に就いている人や、自営業の人、クリエイティブな分野で働いている人などの仕事をしている友人・知人の顔が浮かびました。
ぜひ、家探しと資産運用の両面で、人生を豊かにする一歩を踏み出してください。
▶私が築古戸建てを購入する際、最後まで悩んだインスペクションの話はこちら