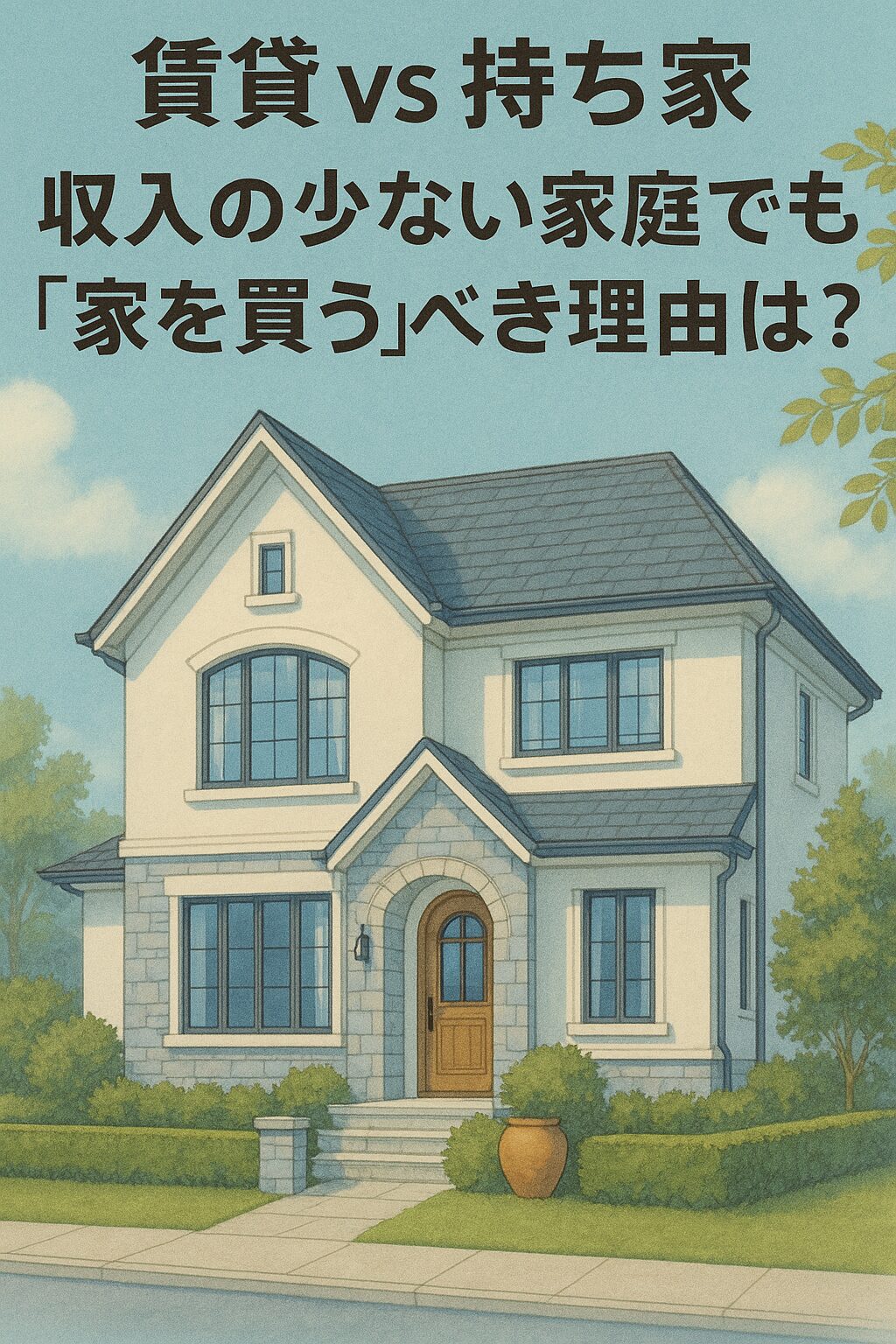こんにちは、ばっきんパパです。
「長年、大切に住んできた家なのに、こんな価格にしかならないの?」
ご自身の親や友人の親御さんから、こうした言葉を聞いたことがある方も多いかもしれません。
私自身もよく耳にしました。思い出の詰まった我が家を売却するとき、「それなりにリフォームもしてきたし、築年数は経っていても、まだまだ住める」と信じていたのに、いざ査定してもらったら「土地値のみ」と言われてしまう。
そこには、制度と実感の大きなギャップがあります。リフォームすると物件価格があがる、それには、前提条件があるのです。
築年数=価値ゼロ? 木造住宅が「消耗品」とされる日本の不動産評価
日本では一般的に、木造住宅は築20~25年で資産価値が“ゼロ”とみなされると言われています。
これには、固定資産税評価や、銀行の担保評価が築年数を基準にしていることが大きく影響しています。
どれだけリフォームをして、設備を最新にしたとしても、「住宅ローンを組む際の担保としては使いづらい」「評価額に反映されない」と言われてしまうケースが多いのが実情です。
これは、戦後の高度経済成長期に生まれた「スクラップ&ビルド」思想の名残で、長く続く経済成長を前提とした住宅流通モデルが、今なお制度として残っているからです。
制度の「穴」──住んだ人の努力やリフォーム費用が無視される
実際、家というのは設備の新しさだけでなく、住み方・手入れの仕方で大きく状態が変わるものです。
リフォームもして、大切に手をかけてきた住宅が「価値ゼロ」と査定されるのは、多くの人にとって納得がいかない話でしょう。
しかし、現行制度では「現地調査も簡易的」「査定も一律の築年数ベース」であることが多く、住まい手の工夫やコストは価格に反映されづらいのが実態です。
築古住宅は、リフォームされていても、中古市場の売買価格には反映されにくいのが現実です。つまり、リフォームに1000万円かけても、その分だけ価格が1000万円上がることはまずありません。
解決策は? リセールを意識して家を選ぶという視点
この状況を逆手に取るとすれば、買うときから「売りやすさ」を意識することが一つの対策になります。
例えば:
- 土地の形状・立地条件が良いエリアを選ぶ
- 築古でも、構造やインスペクションで「安心感」を得られる家を選ぶ
- 間取りや仕様が時代に合っているかどうかを確認する
こうした点を押さえれば、10年後でも一定の価格で売却しやすい家=リセールバリューのある家になる可能性が高くなります。
まとめ|価格だけでは測れない「住まいの価値」
制度的にはまだまだ「築年数重視」な評価が主流ですが、住まいの本当の価値はそれだけでは決まりません。
家族と暮らした時間、手を入れた記録、育ててきた庭、そして地域とのつながり……。
制度が変わらないなら、私たち自身が「正しい知識」と「現実的な見方」を持つことが、後悔しない選択につながるのではないでしょうか。
補足:この記事で伝えたいこと
- 日本の不動産制度は築年数に大きく依存しており、リフォームによる価格上昇は限定的
- 売却価格に驚く人が多いのは、「制度的な前提」と「感情的な価値」のズレがあるから
- リフォームは価格アップではなく、自分たちの暮らしやすさのためにやるもの
続きの中古戸建て記事はこちら
👉 「木造住宅=30年で壊す」はもう古い?令和の今、中古戸建てという選択肢が暮らしを豊かにする